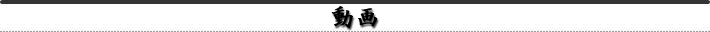第121回 魔法のじゅうたんの原案者と発展(2025.03.06up)
はじめに
見たこともない現象のマジックがあると気分がワクワクします。1987年発行の高木重朗氏と麦谷眞里氏による共著「カードマジック入門事典」は素晴らしい著書です。その中でも「魔法の絨毯」に衝撃を受けました。その現象と原理にカルチャーショックを受けたわけです。しかも、セルフワーキングで出来ることが驚きです。16枚のカードを裏向きに四角形に並べ、大きなKの文字になるように数枚を表向けます。その状態から自由に折りたたんで表裏をバラバラにしたのに、もう一度じゅうたん状に配ると4枚のKだけが表向いています。奇妙なことが、この本のほぼ全ての作品には考案者名が書かれているのに、この作品だけ記載がありません。私を感動させたのに、そのようなことがあってよいのかと思いました。作者不明でも素晴らしい作品であり、そのまま世に出ないのはもったいないので「カードマジック入門事典」に掲載された可能性があります。なお、この作品を取り上げたのは今回が最初ではありません。2018年の第84回フレンチドロップ・コラム「ボブ・ハマー原理の表裏ごちゃまぜとCATO」の中でも報告していますので参考にして下さい。
今回、「魔法のじゅうたん」に関して再度取り上げたのには理由があります。最近になって、ゆうきとも氏の「予兆」を見て感激し、大きな刺激を受けました。同様な現象をじゅうたん状に並べたカードでも行うことができるのではないかと考えました。それを実現するために折りたたみ方を工夫して、1つの法則を見つけることもできました。そして、再度、関連作品や原理についてまとめ直すことにしました。その再調査の中で、あとで報告しますが「魔法の絨毯」の考案者についての驚きのことも分かりました。なお、私の方法に関しては、今年の9月に発行のカードマジックの本に掲載を予定しています。
私の最初の改案と原案者探し
「魔法の絨毯」は私の心をとらえた現象であったので独自の改案を作りたくなりました。このマジックの原理も素晴らしいのですが、それよりも大きなKの文字を使っていたことに魅力を感じていました。1993年の私の著書「スーパーセルフワーキング」では、2段階の現象になる作品を完成させます。4枚のKだけが表向きのじゅうたんで、これをたたんで広げなおすと大きなKのマークが表示されます。客の指示により折りたたんで再度じゅうたん状に並べると、今度は4枚のQだけが表向きで現れます。どちらかといえばマニア向きです。なお、この本の制作時も海外の文献で元の作者を探しましたが見つかりませんでした。
その後、2001年になって「魔法の絨毯」を考案した可能性があるマジシャンが判明します。フランスのRichard Vollmerです。1991年のマジック月刊誌Apocalypse Vol.14 No.3に”Mr. Koenig’s Tapestry”のタイトルで発表されていました。2001年になってApocalypse Vol.11~15の合本が発行されたので解説を見つけることができました。また、1992年のドイツ語版ロベルト・ジョビの本(2008年の英語版では「カード・カレッジ・ライター」の書名)でも同じ現象が発表されていました。こちらでは”Mr. King’s Tapestry”のタイトルになっています。この本により、1991年のフランス語のVollmerの本に解説されていたことも分かりました。これらは日本の解説とは少しですが違いがあります。日本の解説は16枚に4枚のKが含まれているだけですが、Vollmerの方法では10JQKか10QKAの16枚が使われていました。また、表裏状態が逆で、Vollmerは四角形の16枚が表向きで大きなKの文字を裏向きにして開始されていました。
Vollmerによりますと、元になる作品をJean-Yves Prostから見せられてプレゼンテーションやセリフを加えたそうです。Prostはフランスのマジック雑誌”Arcane”を1975年から発行している編集者の一人です。残念ながらProstも誰かから見せられたようで、どこで誰からであったかは覚えていないそうです。さらに残念なのが、Prostから見せられた年数と現象の記載がなかったことです。具体的な改案点の記載がないことにより、大きなKの文字表示がVollmerの考案として確定することができなくなりました。さらに、今回の再調査により、Vollmerではないことがハッキリしました。後で報告しますニック・トロストの作品のクレジットの中で意外な記載があり、そのことからいろいろと分かってきました。
折りたたむこと自体の考案者とその後
この折りたたむ方法の元を調べますと、1917年の英国のHenry Dudeneyの “Amusements in Mathematics” の本になります。モザイク模様やパッチワークテーマのパズルです。また、1926年の「モダンパズル」の本では、Dudeneyが切手のシートを使ったパズルを発表しています。それらのパズルをマジックに応用したのがマーチン・ガードナーです。1971年のThe Pallbearers Review Vol.6 No.9に「パラドックス・ペーパー」のタイトルで発表しています。四角形の紙を16のマス目にして1から16の数を書きます。紙を折りたたんで1マスの大きさにしてハサミで4辺を切って16枚に分割します。16枚を広げると奇数が表向いている状態であれば偶数が裏向きになっています。その応用作品も紹介されています。ダイヤのAから5までの一つを選ばせ、16の折り目がある白紙の5箇所にカード名を記入します。それを折りたたんでハサミで切って広げると、客のカード名のみ表向きに現れます。
カードを16枚使って折りたたむ考え方を最初に言い出したのはカール・ファルブスです。上記のマジック誌The Pallbearers Review の編集者がファルブスであり、ガードナーの方法を解説した後の編者記でカードを使う考えを述べています。ところが、思っていた方法と違っていました。縦や横の一列をひっくり返して重ねる方法ではありませんでした。赤と黒のカードが上下左右とも交互になるように四角形に並べ、1枚のカードを隣のカードの上へひっくり返して重ねます。その2枚が接触しているカードにひっくり返して重ねることを繰り返し、16枚が重なるまで続けます。これによりガードナーと同じ現象の表裏で赤黒を分離させていました。
Richard Vollmerの作品以降の発表作品
1991年にRichard Vollmerが解説した後、折りたたむ現象がいくつか発表されます。しかし、Vollmerのような広げた状態でKの文字となるように表示させてから行うユニークな現象がありませんでした。Kの表示がなく、シンプルにしていたのが2000年のMAGIC誌2月号のレナート・グリーンの”Sweating Bullets”(発汗弾丸)です。彼の方法では、折りたたんで広げると突然に4Aだけが表向きに現れる現象です。覚えやすく演じやすい点が特徴です。4X4の四角形にカードを裏向きに並べますが、左上から右下にかけての斜めの4枚をAにしています。特定の位置の4枚を表向きにして折りたたむだけで4Aだけが表向きになります。なお、4Aはデックのボトムにセットして開始し、ボトム以外がシャフル出来る状態から行っていました。
2004年のジョン・バノンの本では、“Degrees of Freedom” と「折り紙ポーカー」の2作品の折りたたみ現象が解説されています。前者は全ての10JQKAの20枚を使用し、客が選んだマークのロイヤルストレートフラッシュの5枚だけが表向く現象です。後者はシャフルしたデックから16枚を使い、表裏バラバラにしたのにロイヤルストレートフラッシュの5枚だけが表向きます。“Degrees of Freedom” ではボブ・ハマーの原理のCATOを発展させたス ティーブ・フリーマンの考えが応用されています。フリーマンはじゅうたん状に並べていませんが、客にシャフルさせたデックから2枚づつ配りつつ表裏も混ぜる操作を行っています。その後、広げるとロイヤルストレートフラッシュだけが表向きになります。フリーマンが海外でその考えを発表されたことがないと思いますが、日本では1981年からマニアの間で知られていました。1981年にバーノンが来日した時に同行していたのがフリーマンで、その時に演じられました。その考えをジョン・バノンは20枚のパケットを使ってじゅうたん状に並べたことになります。「魔法のじゅうたん」もフリーマンの考えも海外よりも日本の方が先に広まっていたのが意外な点です。
ニック・トロストのジャンボカード使用と驚きのクレジット
2011年のニック・トロスト著 “Subtle Card Creations Vol.3” に解説のQuadraplexでは、ジャンボカードを4分の1に切った16枚を使っています。1枚の普通サイズの予言カードも使います。16枚を四角形に並べ数枚を裏向きにして、客に自由に折りたたませて広げると4枚だけが裏向きます。その3枚を表向けるとジャンボカードのキングが完成しそうです。ところが、4枚目の4分の1が数字のカードであり、失敗したように思います。予言のカードを見ると4分の1が数字カードのキングであることが分かり、予言が当たっていたことになります。折りたたむタイプのマジックで、4分割したジャンボカードの使用は、これが最初かもしれません。日本では、4分割ジャンボカードを使ったシンプルで演じやすい一太郎氏の方法や、その影響を受けられた植木將一氏の方法がありますが、一般には発表されていないようです。
ところで驚いたのは、ニック・トロストの方法が1991年に商品として販売されていたことです。その考案に影響を与えていたのが1989年の日本の高木重朗ビデオ”Card and Coin Magic”の中の「魔法の絨毯」の演技でした。そのビデオを見ますと、演技の冒頭でこの作品のことを報告されていました。1986年にサンフランシスコからアカプルコへ行く時に、バーノン氏からよい奇術だと言って見せてもらったのが「魔法の絨毯」とのことです。カナダ人による方法ですが、その人物名は分からないそうです。記憶に残る名前ではなかったのか、名前が聞き取れなかったのかもしれません。Vollmer氏へ伝えられる元になるのは、高木氏自身がヨーロッパへ行った時に演じられたか、高木氏のビデオが元になる可能性があります。または、カナダの考案者かバーノンにより伝わったのかもしれません。結局、元になる考案がRichard Vollmerでないことだけはハッキリしました。
おわりに
今回この作品を取り上げたのは、じゅうたん状に並べた16枚を使った新しい作品を考案したからです。ゆうきとも氏の「予兆」に似た現象をじゅうたん状に並べて行いました。これまでのじゅうたん状にした作品の全てが、カードを折りたたむのは客の指示か客自身が行っています。新しい私の方法では、客がパケットをシャフルして、客がじゅうたん状に並べますが、演者が折りたたみを行う必要があります。そのことで新しい法則が発見できました。残念なのは、私の好きな大きなKの文字を表示させる見せ方や面白いストーリーが使えなくなったことです。しかし、いろいろと発展性のある「魔法のじゅうたん」ですので今後が楽しみです。
参考文献
1917 Henry Dudeney Amusements in Mathematics
1926 Henry Dudeney Modern Puzzles
1971 Martin Gardner The Pallbearers Review Vol.6 No.9 Paradox Papers
1971 Karl Fulves The Pallbearers Review Vol.6 No.9 編者記 カード使用
1987 高木重朗&麦谷眞理共著 カードマジック入門事典
魔法の絨毯 Flying Carpet 考案者名の記載なし
1991 Richard Vollmer Tours de carts automatiques フランス語
La Tapisserie de Mr. King
1991 Richard Vollmer Apocalypse Vol.14 No.3 Mr. Koenig’s Tapestry
1992 Richard Vollmer Mr. King’s Tapestry
Roberto Giobbi’s Card College Lighter ドイツ語
2008年 英訳版発行 2018年 日本語版発行
1993 石田隆信 Super Self-Working 王家のじゅうたん 2段階現象
2000 Lennert Green Sweating Bullets MAGIC 2月号 方法がシンプル
2004 John Bannon Dear Mr. Fantasy
Degrees of Freedom Origami Poker
2011 Nick Trost Subtle Card Creations Vol.3 Quadraplex