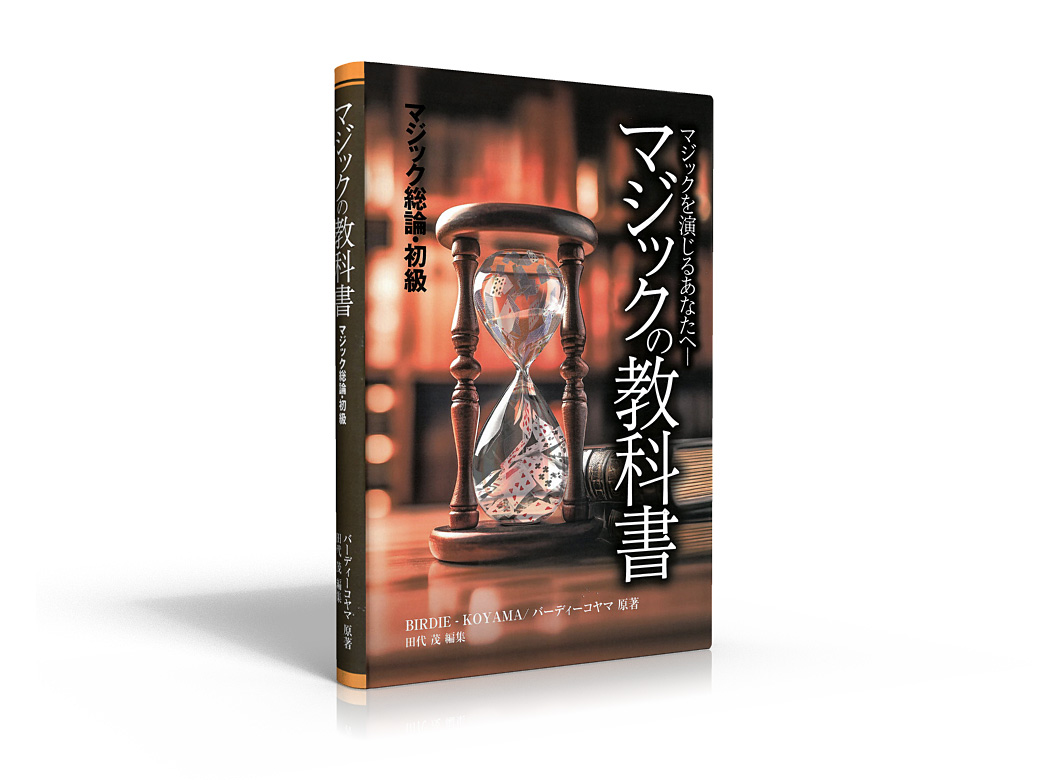“演じる”ことの本質に迫る、マジックを芸に高めるための入門書
本書は、単なるマジックの種明かし本ではありません。登場から退場までの所作、目線、姿勢、立ち振る舞いなど、プロフェッショナルとして舞台に立つために必要な「見せ方の技術」を、丁寧に解説しています。舞台に立った瞬間から退場するまでの一挙手一投足――登場時の足運びや姿勢、観客との目線の合わせ方、間の取り方、そして静かに幕を下ろす所作に至るまで――すべてが観客に与える印象を左右します。本書では、こうした見過ごされがちな所作の意味や美しさを、豊富な具体例と共に丁寧に解説。観客の心をつかむ「芸としてのマジック」を成立させるために、パフォーマンス全体をどう設計し、どう見せるべきかを学べる内容になっています。
著者が優れた表現者であるので、テキスト説明で十分に理解できますが、より揺るぎのない理解のため、QRコードから30本の補足動画が視聴可能。読んで、見て、理解するというハイブリッドな学びを実現しています。
さらに第2部では、約3800年前の古代エジプトから現代まで、世界のマジック史をコンパクトに紹介。資料的価値も高く、芸としてのマジックに関心のある方にとっては貴重な内容となっています。
マジックを「芸」として真剣に学びたいすべての方にとって、まさに必読の一冊です。
本書はトリックの解説書ではなく、マジシャンの解説書であり、マジシャンの作り方が記されている極めて良書です。全てのマジシャン、マジシャンになろうとする方に 心からおすすめできるバイブル。
唯一つ、気になるのは初級となっていること。 果たして、中級、上級があるのでせうか? 初級の本書でかなり満足しているのでありました。
HIRO SAKAI
「マジックの教科書」は、通り一遍の指導書ではありません。バーディーコヤマ師の長年の舞台活動から導き出した答えが満載です。 特に、ダニー・コールとエイモス・レフコヴィッチの演技を詳細に分析して解説している部分は、師が芸能をどう捉えているのか、心の告白が見えて感動します。 久々の名著です。
藤山 新太郎
「何十年やっていても下手は下手、キャリアが浅くても上手い人は上手い」。実演に対して基礎が欠かせないとして7項目にまとめて解説されています。30のQRコードの映像も加えられているのが特徴です。
最後の27ページにわたる「マジシャン人生を振り返って」では昔の記憶を鮮明に報告されています。特に華やかなキャバレー時代の出演料が高くても出費も多く、実際の金額を公開して報告されていたのが興味深い点です。当時は生演奏しかなく、楽団とのやりとりの生々しさも印象的です。師匠は村上正洋師で村上流の考えが随所に登場し、演じるための基本とプロとしての基本が詰まっています。
1969年にプロとなり、1978年までの10年間はキャバレーやナイトクラブ出演、1979年から札幌マジックキャッスルを任され1980年には買い取っています。1990年にはマジックバー「マジックハウス」を開店され、結局札幌で38年間活躍されました。イリュージョンからマニピュレーション、クロースアップ、そしてメンタルマジックまで演じられています。
2023年10月に開催された「特別講習会」は、タネ明かし講習ではなく、実演を交えながらのマジックの演技のことと歴史の解説でした。 その講習に感銘を受けた田代茂氏が、その時の冊子に肉付けを行い書籍の形にされました。マジックの歴史に関しては田代氏が大幅に加筆され、各年代に活躍されたマジシャンの簡潔な紹介が大いに参考になります。 この「マジック教科書」はマジックの解説書ではなく、マジックを演じるための総論としての価値が高く是非読まれることをお勧めします。
石田 隆信
本書は種明かしの本ではありません。ネット時代の今、マジックのタネであれば少し検索するだけで、数千、数万のネタを拾い出すことができます。しかし、芸事にはいくら検索しても学べないものがあります。本書はこれまでほとんど触れられなかった立居振舞、具体的には「登場」「お辞儀」「退場」「目線」「立ち姿とポーズ」「芸としての見せ方」や「意味」「思想」他、師匠から直接指導を受けるしかなかったことが数多く解説されています。
「守・破・離」という言葉があります。茶道や芸道でその道を究めるためのステップです。本書は「人前でマジック演じたい」方にとって、その第一歩、「守」をしっかり教えてくれます。 「破」や「離」は個人の才能に寄るところも大きいのですが、「守」の部分は誰もが学ぶべきことばかりです。人前で演じるのであれば、どうしても知っておかなければならないことが、まるでかゆいところに手が届くといった具合に解説されています。
第2部「歴史」では、今から約3800年前に書かれたエジプトのパピルスに、ファラオの前で行われたマジックの話から、二千数百年前、中国で行われていた「幻戯(めくらまし)」と呼ばれる芸能の話、江戸時代より前の日本で行われたマジック、1700年代から1900年ごろのヨーロッパで行われていたマジック、1931年ごろから1960年代、さらにそれ以降、2000年代はじめくらいまでのマジシャンや演じていたものが30数ページを費やし、コンパクトにまとめられています。
さらに特筆すべきこととして、本書にはQRコードが30あり、読みながらすぐにスマホなどで、実際の演技を確認できます。これは画期的です。CDやDVDのように、全編動画として観るのではなく、今読んでいるところを補足する意味で動画が差し込まれています。読んでいるとき、文章だけでは伝わりにくいところがスマホなどで、観られるようになっています。紙というメディアと動画というメディアをうまく合体させたすばらしいアイディアです。
バーディーコヤマさんが現在(2025年)、76歳のはずですが、凛とした立ち姿は、あいかわらず美しく、立っているだけで絵になります。これは意識し、訓練を受けた人にしかできません。 また本書はバーディーコヤマさんの原著を元に、田代茂さんが編集されたものとなっています。それもあり、データなども信頼できるものばかりです。芸としてのマジックを習得したい方は勿論、第2部の「歴史」は、多少ともその分野に関心がある方にとっては、貴重な資料となると思います。
マジェイアの魔法都市案内 三輪晴彦
今、私のように弟子入りをせず、マジックの道に進んで活動していらっしゃる方も多いと思います。ありがたいことに私は、子どもの頃からマジックのタネを学ぶことや、道具を入手することが容易な時代を過ごすことができました。ですが、「同じことをやっているはずなのに、この人はどうしてプロっぽいんだろう? と感じたり、うまく言い表せないけれど、大きな違いを感じることが多々ありました。今回、この本を読んで「なるほど、こういうことだったのか!」と、目から鱗が落ちるような部分がたくさんありました。失礼ながら、お名前くらいしか存じ上げていなかった村上 正洋師の「村上流」といわれる教えが、日本奇術界の1つの礎を築いてきたことがよく分かりました。
貴重な教えを本に残してくださったバーディーコヤマ師、田代茂師には、個人的にも心から感謝を申し上げます。そして、最後のページのバーディー師のお写真が異次元のかっこよさです。ぜひ皆さん、最後まで楽しみにお読みください。
渋谷 駿
-

マジックと意味 増補版 【日本語版】
10万円前後の高値で取引される貴重本。その日本語版です。
-

マジック本では学べないマジックの秘訣 52
観客を楽しませ、満足させるために必要な技術がここに。
コヤマさんが最初に注意点として記載されている様に、本書はマジックを演じる人に向けた本となります。内容としてはステージ系になるのかも知れませんが、クロースアップを演じる場合でも書かれている内容は非常に参考になります。推薦文にもあるように、各項目で文章のみの説明では分かりにくい箇所にはコヤマさん本人や有名なマジシャンの実演映像がリンクされています。コヤマさんの映像は、相手に分かりやすくなるように構成されており理解度が上がります。フレドロさんでも取り扱われている洋書や翻訳本も参考になるようにタイトルと参照するページが記載されているのも良書たる理由です。音楽、照明、衣装の項目はこれまでに無い具体的な記載がされており勉強になりました。
海外のマジシャンが執筆された本は、日本語で翻訳されていても感覚的に違和感があることがありますが、コヤマさんの本ではそのような感じはなくスーッと体の中に入ってくる心地良さがあります。この辺りは、肉付けされた田代さんの力なのかもしれません。タイトルに教科書や初級の文字がありますが、中級者以上の方にもお勧めします。
マジックの歴史はコンパクトながら時系列で整理されており、知識が広がります。コヤマさんの人生振り返りでは、ただただスゴイとしか表現できません。
また、本離れが進む中、田代さんには翻訳本や本書のようなレクチャーノートからのハードブック化とマジックを広めるための活動に大変感謝しています。価格は高いと感じるかもしれませんが、内容とハイブリッド型の取り組みをされているので購入されて損はありません。1人でも多くのマジックを演じる方に購入してほしいと切に願っています。